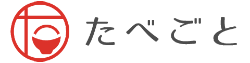目次
 雪平鍋は、打ち出し模様が特徴的な、注ぎ口付きの片手鍋。安価なものが多く、使える範囲も広いので、調理器具を買うときのファーストチョイスの一つです。重ねておけるので、サイズ違いでいくつか持っていても便利ですよ!
雪平鍋は、打ち出し模様が特徴的な、注ぎ口付きの片手鍋。安価なものが多く、使える範囲も広いので、調理器具を買うときのファーストチョイスの一つです。重ねておけるので、サイズ違いでいくつか持っていても便利ですよ!雪平鍋の由来やメリットって?
 雪平鍋は行平鍋とも書きます。打ち出し模様と注ぎ口のある片手鍋を言いますが、中には打ち出し模様がなく、注ぎ口のある片手鍋を雪平鍋と呼んでいる場合もあります。
雪平鍋は行平鍋とも書きます。打ち出し模様と注ぎ口のある片手鍋を言いますが、中には打ち出し模様がなく、注ぎ口のある片手鍋を雪平鍋と呼んでいる場合もあります。ここでは、雪平鍋の歴史を少し紐解いてみましょう。
雪平鍋の歴史
戦前までは「雪平鍋」というと陶製の注ぎ口付きの鍋のことでした。陶製の雪平鍋は、天明(1781~1789)末頃から作られるようになったという説があります。現在のアルミやステンレス、銅でできた雪平鍋は、戦後に生まれたものと言われています。
雪平鍋の模様のメリット
雪平鍋の打ち出し模様はただの飾りではありません。この模様のおかげで鍋は強度を増し、熱伝導率を上がるというメリットが生まれています。以前は、手打ちで作っているものが主流でしたが、現在は機械で打ち出しているものがほとんどです。
とは言え、本手打ちの雪平鍋も高級品として残っています。独特の味わいが人気です。
名前の由来
その1. 模様から名づけられたという説
でこぼこした打ち出し模様が雪の降る様子に似ているため、この名が付いたと言われています。その2. 在原行平から来ているという説
在原行平(ありわらのゆきひら)は平安時代の歌人。『伊勢物語』で有名な在原業平の兄でもあります。この行平には、須磨で塩焼きの海女と親しんだという故事があります。この海女が塩焼きに使っていたのが器が由来ともされています。
ちなみに行平と塩焼き海女との話は、能の名曲「松風」にも描かれています。
能・演目事典『松風』
その3. 煮物の湯気を表しているという説
 煮物から立ち上る湯気を「湯気平(ゆげひら)」と表し、そこから「ゆきひら」に変化したとされています。
煮物から立ち上る湯気を「湯気平(ゆげひら)」と表し、そこから「ゆきひら」に変化したとされています。雪平鍋の使い方|雪平鍋で作る料理
 雪平鍋は熱効率が高く、均一に熱が回るため、どんな料理にも使いやすい鍋です。
雪平鍋は熱効率が高く、均一に熱が回るため、どんな料理にも使いやすい鍋です。だしを取る
 水がすぐに沸くのでだしを取るときに重宝します。
水がすぐに沸くのでだしを取るときに重宝します。野菜を湯がく
青菜をさっと湯がくときにも便利!茹でこぼすときも、注ぎ口があるのでお湯が捨てやすいので楽々。煮物を作る
打ち出し模様によって、熱が均一に伝わるため煮物に最適です。落し蓋を用意すれば、煮魚にも!
フランス料理やイタリア料理のソースに
 注ぎ口があり、片手で軽々と持てるのでソースを作ってそのまま料理に回しかけるのに便利!
注ぎ口があり、片手で軽々と持てるのでソースを作ってそのまま料理に回しかけるのに便利!和食や中華のあんを作るのにも向いています。
インスタントラーメンに
 さっと作って、さっと食べたい!というときに活躍します。たっぷりのお湯で茹でるパスタには向きませんが、生麺のうどんを作るのにもいいですね。
さっと作って、さっと食べたい!というときに活躍します。たっぷりのお湯で茹でるパスタには向きませんが、生麺のうどんを作るのにもいいですね。