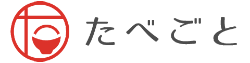目次
 生後100日のお祝いの儀式である「お食い初め」。近年ではイベント化しつつある子どもの成長を祝う行事ですが、育児真っ只中で職場復帰し共働きしている忙しいご家庭では、その準備も一苦労ですよね。そこでこの記事ではネットでお取り寄せできる人気の「お食い初めセット」をご紹介。お食い初めに関する知識もこの記事で網羅できますよ。
生後100日のお祝いの儀式である「お食い初め」。近年ではイベント化しつつある子どもの成長を祝う行事ですが、育児真っ只中で職場復帰し共働きしている忙しいご家庭では、その準備も一苦労ですよね。そこでこの記事ではネットでお取り寄せできる人気の「お食い初めセット」をご紹介。お食い初めに関する知識もこの記事で網羅できますよ。お食い初めとは?

どんな儀式?
「お食い初め」という儀式について、身近に赤ちゃんが生まれてから知った方も多いのではないでしょうか。お食い初めとは「子供が一生食べ物に困らないように」「丈夫な歯が生えるように」という願いを込めて、赤ちゃんに初めて、食事の真似をさせる儀式です。赤ちゃんのこれから先の成長を願い、成長段階に合わせて行う儀式のひとつとして、平安時代から行われてきました。
お食い初めは生後100日を目安に行います。しかし、生後3~4ヶ月の頃のこの時期は、赤ちゃんはまだミルクの時期。固形物は食べられません。「お食い初め」とは言いますが、口元に食べ物を持っていき、食べるフリだけで、米一粒でも口のなかに入ればおめでたい、という儀式なのです。
お食い初めの儀式には、赤ちゃんの両親のほかに祖父母も招待して行うことが多いです。必要な道具やお料理などを揃えて自宅で済ませるご家庭が多いようですが、なかには料亭などで盛大に行うご家庭もあるそうです。生後100日前後の赤ちゃんなので、赤ちゃんの負担を考えると自宅で行うほうがよいかもしれません。
平安時代から続く「お食い初め」の歴史
医学が未発達だった昔は赤ちゃんが健やかに育つ確率はとても低かったため、赤ちゃんがひとつ節目を迎えるたびに家族で喜び、お祝いしたのだそうです。お食い初めも、そのような赤ちゃんの成長をお祝いする儀式の一つです。お食い初めの起源は、平安時代にまでさかのぼります。その当時は生後50日目と生後100日目に餅を重湯のなかに入れ、箸を使って子どもに食べさせる「五十日百日の祝い」というのがあり、このお祝い事が現在の「お食い初め」の原点となっています。
鎌倉時代には餅ではなく魚を食べさせるようになり、「真魚の祝(まなのいわい)」と呼ばれるようになったそうです。