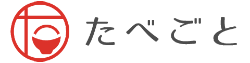お食い初めの一般的なやりかた

食べさせ方の順番
赤ちゃんに食べさせるときには「お赤飯→汁もの→お赤飯→焼き魚→お赤飯→汁もの」と、お赤飯始まりでほかのものを食べさせるようにするのが順番とされています。最後に歯固めの儀式をします。食べさせるのは誰?
赤ちゃんに食べさせる役は、「養い親」と呼ばれる人がやります。養い親とは、両親ではなく、親戚一同のなかで最年長の方のこと。赤ちゃんの長寿を願う儀式なので、長寿にあやかるという意味で、昔から養い親がその役割を担っていたようです。現在では、親戚がなかなか近くに住んでいないこともあり、祖父母のどなたかが「養い親」役をすることが多いです。食べさせるときには、養い親と別な人が赤ちゃんを膝に座らせた状態で食べさせるフリをします。地域によっては、男の子は男性の養い親のひざに、女の子は女性の養い親のひざに座らせると決まっていることもあるそうです。
お食い初めの儀式に親戚を呼んだほうがよい?
お食い初めの儀式には、養い親になってもらう祖父母を招待しましょう。各ご家庭での祖父母との距離の取り方によりますが、どちらの祖父母に養い親をお願いするのか、どちらの祖父母も招待するのか、のちのち揉めないためにも、事前に話し合って決めておきましょう。また、最近では100日祝いで記念撮影をする家庭もあります。写真館によっては「お食い初め撮影」のためのプランなども準備されています。衣装や装飾類を借りることができるので、お食い初めで記念撮影も検討しているのであれば、写真館のプランなども確認してみましょう。
どんな食材を食べるの?

基本は一汁三菜
お食い初めでは、「一汁三菜」を基本とした祝い膳を用意します。「一汁三菜」とは、ごはんの他に汁物が1品とおかずが3品つく食事を指します。おかず3品は、メインとなるお魚料理を1品と、副菜、箸休めを1品ずつで構成されることが多いようです。「一汁三菜」のなかには、季節の食材やその地域ならではの食材が用いられます。いずれも、縁起のよい食材をたくさん取り入れられています。以下はひとつの祝い膳のメニューの例ですが、祝い膳のひとつひとつの品に込められた願いについて知っておきましょう。
【ごはんもの】赤飯
魔除けや厄払いの力があるといわれている赤を使った「赤飯」は、赤ちゃんがこれから病気になることなく、健やかに育ちますようにという願いが込められています。【汁物】貝のお吸い物
ハマグリなど貝を使った汁物は、良縁を意味する縁起物です。将来二枚貝のようにぴったり合う伴侶を見つけられるように、という意味が込められています。また、お吸い物は「吸う力」が強くなるように、という意味もあります。【主菜】祝い鯛
鯛はみなさんも知ってのとおり「めでたい(鯛)」という語呂にちなんだ縁起物。見た目は赤く、中の身は白い色をしていることから、紅白の色としても縁起がよく、お祝い事には欠かせない魚として日本では古くから食べられています。お祝いでは、おかしらがついた1匹の状態を準備しましょう。【副菜1】煮物
副菜の煮物には、煮しめや黒豆やエビとレンコンの吹き寄せなどが挙げられます。エビとレンコンの吹き寄せは、長寿と先行きの明るさを願う煮物。おせちにも入っている黒豆は、まめに生きるという意味があります。【副菜2】香の物、箸休め
もう一つの副菜としては、季節の野菜を漬けた香の物や酢の物を準備します。大根なますなど、彩りがあるものがいいでしょう。お食い初めの儀式をするのに準備するもの

歯固めの石
歯固めの石は、石に触れた箸で赤ちゃんの口に触れる「歯固め」の儀式で使う石のことをいいます。「石のようにかたく、丈夫な歯が育つように」という意味を込めて行う儀式で、歯が生え始めるのが100日前後なため、100日祝いであるお食い初めの儀式のなかですることが多いです。歯固めの石は2~5cm程度の大きさの小石で、丸みを帯びてつるんとしているものが2~3個あればよいでしょう。石の形や個数は、その地域のしきたりがあるかもしれないので神社などで聞いてみましょう。
最近では赤ちゃんが初宮参りをした神社にお願いして借りるのが一般的です。神社で手に入らなければ、西松屋やトイザらスなどベビー用品を扱うお店で販売しています。お食い初めの食器のレンタルや、食材を通販で取り寄せる場合には、それらのなかに歯固め石が含まれていることもありますよ。
また、歯固めの石といいますが地域によっては本物の石ではなく食べ物を使うこともあります。梅干し、タコ、鬼胡桃、アワビ、紅白餅などです。
歯固め石は使い終わったら、借りた場所(神社や川原など)にお返ししましょう。購入した場合は記念に取っておくのもよいでしょう。
祝い箸
お食い初めは、初めて箸を使うことから「箸揃え」「祝い箸」「お箸初め」とも呼ばれます。祝い箸というのは祝い膳に使うお箸のことで、八寸(24cm)の長さの柳の木で作られた箸で、両端が細くなるように削られています。この八寸(24cm)の長さには理由があり、日本や中国では八という字が下のほうに向けてしだいに広がっていて、末広がりの形をしていることから、縁起を担ぐ意味でその長さとなっています。
祝い箸は、水引つきの箸袋に入ったものがいくつかセットになって、楽天などの通販で気軽に購入できます。また、百貨店やお箸の専門店などでも手に入れることができますよ。
服装
100日のお祝いの儀式であるお食い初め。赤ちゃんの服装のことを忘れてはなりません。お食い初めの儀式に特に服装の決まりはありません。ご家庭によって自宅で済ませる方もいれば、写真館で撮影する方もいるし、料亭で親戚を呼んで行うこともあります。料亭や写真館などで格式ばった儀式を行う場合には、祖父母、両親もスーツやワンピースで格をそろえ、赤ちゃんには和装ならば小袖、洋装ならばドレスやタキシードを着せて統一感を出すのがよいでしょう。
しかし、赤ちゃんが食べ物をこぼしたり汚したりすることを考えると、着替えさせたりオムツを取り替えるのが大変です。着物や袴デザインのロンパースや、ドレスやタキシード風のベビー服でもよいでしょう。ご自宅でお食い初めをするならそれで十分です。
食べさせる真似とはいえ、念のためにスタイは必ずするようにしましょう。
男の子と女の子で異なる、お食い初めのならわし

お食い初めの食器はどんなもの?
お食い初めの食器は、正式には柳の白木箸、塗りの漆器、家紋が入った高足のお膳に食事を盛り付けます。とはいえ漆の食器をそろえても、記念にはなるけれど赤ちゃんの食事の普段使いにはならないですよね。お食い初めだけでなく、節句などもお膳でお祝いしたいのなら一式そろえるのもいいですが、最近では新品の木製や陶器製のベビー食器で代用するご家庭が増えているそうです。
男の子と女の子でどこが違う?
正式なお食い初めの儀式では、男の子と女の子によって、使う食器の塗りの色が異なります。男の子は内外とも赤色で金か黒漆で男紋が入っているもの、女の子は外側が黒、内側が赤で銀の女紋が入っているものを使用します。漆器ではなく、木製や陶器製のベビー食器を使用する場合には、男女の違いにこだわらず、兄弟でも使えるようなデザインのものがよいでしょう。
地域によってさまざまな呼び方がある、お食い初め
 お食い初めは、「百日の祝」や「真魚の祝」など、地域によってさまざまな呼び方があります。この理由には、生後100日というのが成長の節目であるとともに、地域性によって呼び方も変わっていったといわれています。
お食い初めは、「百日の祝」や「真魚の祝」など、地域によってさまざまな呼び方があります。この理由には、生後100日というのが成長の節目であるとともに、地域性によって呼び方も変わっていったといわれています。例えば、「歯固め」というのは生後100日頃から歯が生え始めるため、丈夫な歯が育つようにという願いを込めたお食い初めの呼び名です。また、「箸始め」「箸初め」「箸揃え」というのは、お食い初めで初めて赤ちゃんが箸を使うことから呼ばれた名前です。
生後100日経つと、赤ちゃんは生まれたときの体重の2倍の重さになり、首も据わって、顔つきもしっかりしてきます。赤ちゃんにとって成長の節目となるお食い初めの儀式は、成長が目に見えて感じられる心温まる儀式です。