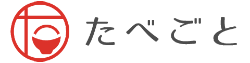目次
 毎朝、家族でコーヒーを飲むときも、夕食を食べるときにも使うマグカップ。それぞれがお気に入りのマグカップを使っていて、食卓には個性があふれています。実際に、マグカップを買いに行くときも種類や大きさ、デザインも多種多様でどれにしようか迷ってしまうくらいです。そんな日常生活に欠かせないマグカップが、使いやすい食器として人気のある「波佐見焼」を一躍有名にしたことをご存じでしょうか?今回は波佐見焼を代表するデザインのマグカップから、シンプルでおしゃれなものまでご紹介します。
毎朝、家族でコーヒーを飲むときも、夕食を食べるときにも使うマグカップ。それぞれがお気に入りのマグカップを使っていて、食卓には個性があふれています。実際に、マグカップを買いに行くときも種類や大きさ、デザインも多種多様でどれにしようか迷ってしまうくらいです。そんな日常生活に欠かせないマグカップが、使いやすい食器として人気のある「波佐見焼」を一躍有名にしたことをご存じでしょうか?今回は波佐見焼を代表するデザインのマグカップから、シンプルでおしゃれなものまでご紹介します。日常使いのうつわ制作が得意!人気の波佐見焼について
 波佐見焼は、長崎県波佐見町で作られているうつわです。マグカップからプレート、お茶碗などの日常の食卓で並ぶような食器を作っています。形や絵付けのデザインは窯元ごとに異なり、カラフルな可愛らしいものからシンプルでかっこいいもの、グッドデザイン賞を受賞したものまで幅広くあります。きっと、おうちの食卓にぴったりの一品を見つけることができますよ!
波佐見焼は、長崎県波佐見町で作られているうつわです。マグカップからプレート、お茶碗などの日常の食卓で並ぶような食器を作っています。形や絵付けのデザインは窯元ごとに異なり、カラフルな可愛らしいものからシンプルでかっこいいもの、グッドデザイン賞を受賞したものまで幅広くあります。きっと、おうちの食卓にぴったりの一品を見つけることができますよ!そんな波佐見焼は、戦国時代に豊臣秀吉が朝鮮の陶工・李祐慶兄弟たちを日本に連れて帰ってきたことからはじまりました。江戸時代の頃には、庶民の食器「くらわんか碗」と醤油やお酒などの輸出用ボトルとして「コンプラ瓶」が大量生産されていました。特に、「くらわんか碗」は大量生産されたことによって価格が下がり、庶民にも手の届く食器となりました。