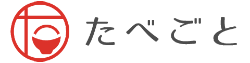目次
 あきたこまち、コシヒカリなど有名な品種を含め、お米の品種は約440種もあるそうです。そんな数あるお米の中で、「ササニシキ」という品種をご存知でしょうか。スーパーや精米店で目にすることは少なくなっていますが、ササニシキはひと昔前に宮城県を中心に東北地方で多くつくられていた品種。あっさりとした味わいが和食にマッチするのできっとファンも多かったと思います。生産量の減少の背景や特徴、後継品種などササニシキの今をお伝えします。
あきたこまち、コシヒカリなど有名な品種を含め、お米の品種は約440種もあるそうです。そんな数あるお米の中で、「ササニシキ」という品種をご存知でしょうか。スーパーや精米店で目にすることは少なくなっていますが、ササニシキはひと昔前に宮城県を中心に東北地方で多くつくられていた品種。あっさりとした味わいが和食にマッチするのできっとファンも多かったと思います。生産量の減少の背景や特徴、後継品種などササニシキの今をお伝えします。ササニシキはどんな米?産地や特徴について
ササニシキの産地
 ササニシキは宮城県で生産が盛んだったお米の品種です。現在もひとめぼれに次いでつくられていますが、作付けの面積はかなり限られているそう。現在、宮城県で力を入れて栽培している主力米は「ひとめぼれ」。ササニシキの代わりに生産量が増加した品種です。ただし、宮城県では多品種生産を奨励されていることもありササニシキも面積こそ減りましたが、まだまだ人気の高いお米として栽培されています。
ササニシキは宮城県で生産が盛んだったお米の品種です。現在もひとめぼれに次いでつくられていますが、作付けの面積はかなり限られているそう。現在、宮城県で力を入れて栽培している主力米は「ひとめぼれ」。ササニシキの代わりに生産量が増加した品種です。ただし、宮城県では多品種生産を奨励されていることもありササニシキも面積こそ減りましたが、まだまだ人気の高いお米として栽培されています。宮城県以外の産地には、山形県、秋田県、岩手県、福島県の一部など、主に東北地方で栽培されています。しかし、宮城県での生産量が徐々に減少していったことで、生産量の少ない希少米になりつつあるようです。
ササニシキの味を活かした料理
 ササニシキは、あっさりとした上品な味わいのお米だと言われます。特有のクセがなく料理の味を引き立たせてくれる品種なので、こってりした味付けのフレンチや中華料理よりも、日本食のようなだしが決め手の料理には最適。お米としての主張は控えめなのかもしれませんが、ササニシキ本来の素朴な味わいは、非常に和食向きだと言えるでしょう。
ササニシキは、あっさりとした上品な味わいのお米だと言われます。特有のクセがなく料理の味を引き立たせてくれる品種なので、こってりした味付けのフレンチや中華料理よりも、日本食のようなだしが決め手の料理には最適。お米としての主張は控えめなのかもしれませんが、ササニシキ本来の素朴な味わいは、非常に和食向きだと言えるでしょう。また、お米に粘り気が少ないのも特徴の一つで、食べると口の中でほろっと崩れるような食感がします。このちょうど良いお米のほどけ具合が寿司米にぴったりで、お寿司屋さんでは今も、提供するお米は「ササニシキ」とこだわっているお店も多いようです。
消えたササニシキの今
昔はコシヒカリのライバルだった

生産量が激減したのはなぜ?
 ササニシキは元々、「病気に強くてたくさん穫れる米」として1963年に宮城県で開発された品種。父親の「ササシグレ」と母親の「ハツニシキ」から名前をもらい、コシヒカリとは兄弟親戚品種にあたります。当初は開発された目的通り、東北地方の寒さにも耐えられ、病気に強く、収穫量も多い品種として栽培する農家が増加しました。
ササニシキは元々、「病気に強くてたくさん穫れる米」として1963年に宮城県で開発された品種。父親の「ササシグレ」と母親の「ハツニシキ」から名前をもらい、コシヒカリとは兄弟親戚品種にあたります。当初は開発された目的通り、東北地方の寒さにも耐えられ、病気に強く、収穫量も多い品種として栽培する農家が増加しました。ところが、1993年に全国的な異常気象が発生。北海道から東北地方までは特にひどい冷害に遭ったのです。この時、寒さと病気に強い品種として認知されていたササニシキは、実は適切な条件下では最高品質のお米が出来るものの、栽培する土壌や気候によっては冷害や病気にも弱いということが知られるようになったのです。その後、寒さに強い「ひとめぼれ」が注目され、作付け面積はササニシキからひとめぼれへとシフトしていきました。