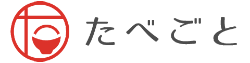曲げわっぱを見て最初に思ったのは、「木ってこんなに曲がるんだ」ということ。では実際にどうやって曲げわっぱが作られているのか、簡単にご紹介します。
曲げわっぱを見て最初に思ったのは、「木ってこんなに曲がるんだ」ということ。では実際にどうやって曲げわっぱが作られているのか、簡単にご紹介します。1.「はぎ取り」
側面に使う製材した部材の両端を薄く削ります。この薄浮くした部分は、側面の板を曲げた時につなぎ目になるところです。木を曲げて端を合わせたとき全体が均一な厚さになるように加工します。
2.「煮沸」
はぎ取りした板を湯船につけて80度になるまで煮ます。きれいに曲げるために水分を吸わせます。
3.「曲げ加工」
湯船から板を引き上げたら、丸太に添わせてクルクル巻いていきます。それはまるで、巻物をクルクル巻いていくかのように曲げていきます。丸太である程度、曲がってきたら、規定サイズの型に巻きつけ、大きなクリップのような留め具で木を型に固定します。
4.「乾燥」
曲げた部材を1週間以上かけて乾燥し、形を定着させます。
5.「接着」
接着材をつけて、先ほど登場した大きな木製の留め具で固定。1日乾かします。
6.「底入れ」
接着した曲げ板に底板を入れていきます。板をはめ、トンカチで軽く全体を叩き調整します。
7.「桜皮とじ」
最後に接着部分を桜の木の皮で綴じます。
実は簡単!曲げわっぱのお手入れ方法
 曲げわっぱは、きちんと使い方とお手入れをすれば、何十年も使えます。お手入れといっても難しいことはありません。いつもの食器洗いに少しの思いやりを持つだけで大丈夫です。お手入れのポイントを簡潔にご紹介します。
曲げわっぱは、きちんと使い方とお手入れをすれば、何十年も使えます。お手入れといっても難しいことはありません。いつもの食器洗いに少しの思いやりを持つだけで大丈夫です。お手入れのポイントを簡潔にご紹介します。塗装されていない曲げわっぱの場合
- ・柔らかいスポンジなどでやさしく擦り、ぬるま湯で洗い流します。
- ・木に吸収されてしまうため、洗剤は使いません。
- ・汚れがこびりついていたら、かためのスポンジの角で落とします。
- ・昔ながらの研磨剤入りのクレンザーとたわしを使ってもOK。丁寧に隅まで洗いましょう。ただし、塗装してある曲げわっぱには絶対に使わないでください。傷がついて、そこからカビてしまうこともあります。
- ・風通しの良い場所で乾燥させましょう。(丸1日以上)

漆塗りの曲げわっぱの場合
- ・柔らかいスポンジなどを使って、洗剤で洗い流します。漆塗りなので、洗剤で洗って大丈夫です。
- ・布巾やタオルで水気を拭き取ります。
- ・風通しの良い場所で乾燥させます。(丸1日以上)
新しい曲げわっぱを購入したらアク抜きをしましょう!
- ・80〜90℃のお湯に30分〜1時間つけておきます。
- ・曲げわっぱが浮いてくるので、重石を乗せることをお忘れなく。
- ・つけていたお湯に色がついていれば、アクが出たサインです。
- ・曲げわっぱの水気を十分に拭き取って、風通しの良いところで乾燥させましょう。
電子レンジで使える?使用上の注意
 ほとんどの曲物は木製のため、電子レンジは使用できませんと明記されています。しかし、ほんの一部ですが、電子レンジが使える曲物もあります!そんな弁当箱をご紹介します。
ほとんどの曲物は木製のため、電子レンジは使用できませんと明記されています。しかし、ほんの一部ですが、電子レンジが使える曲物もあります!そんな弁当箱をご紹介します。プラスチック製の曲げわっぱ風お弁当箱
こちらの弁当箱は、見た目が曲げわっぱに見える、プラスチック製の弁当箱です。電子レンジを毎日使いそうな方はこちらのような弁当箱も選択肢の一つに入れてもいいのではないでしょうか?・内容量総容量:520ml(上段220ml、下段300ml)
・材質:飽和ポリエステルとABS樹脂の成型品カラー溜
・生産国:日本製
電子レンジOK!尾鷲わっぱ
三重県尾鷲市で作られている尾鷲わっぱ。こちらの曲げわっぱは、尾鷲ヒノキや国産漆を使って作られていますが、職人の奥様が2年間毎日、電子レンジに入れても壊れなかったというお墨付きの一品です。電子レンジ対応曲げわっぱはとても少ないので、貴重です!曲げわっぱのルーツを探ろう
 そもそも、曲げわっぱの「わっぱ」という言葉は「曲物(まげもの)」の方言です。曲げわっぱの産地として有名な秋田県では「大館曲げわっぱ」と言いますが、静岡県では「井川メンパ」、福岡県では「博多曲物」と呼ぶそうです。いろんな呼び方があって楽しいですね。
そもそも、曲げわっぱの「わっぱ」という言葉は「曲物(まげもの)」の方言です。曲げわっぱの産地として有名な秋田県では「大館曲げわっぱ」と言いますが、静岡県では「井川メンパ」、福岡県では「博多曲物」と呼ぶそうです。いろんな呼び方があって楽しいですね。曲げわっぱが人々の生活で使われはじめたのは、奈良時代から。木こりが杉を曲げ、桜の木の皮で止めたものが最初の曲物だと言われています。時は平安、鎌倉と流れ、戦国時代。現在の秋田県大館市では、関ヶ原の戦いの後、大館城主となった佐竹西家が、領内の豊富な森林資源を利用して貧しい状態を打開するために下級武士たちに命じて、副業として曲げわっぱの製作を奨励しました。完成した曲げわっぱ製品は酒田・新潟・関東等へ運ばれていったそうです。「大館曲げわっぱ」全国で唯一、国の伝統工芸品として指定されています。
秋田の大館以外も!曲物の産地について
静岡県 井川メンパ
 静岡県静岡市の最北の地区・井川。南アルプスへの入り口でもあるこの地域で、弁当箱「井川メンパ 」は作られてきました。ヒノキの曲物に漆をしっかり塗り込んでおり、その丈夫さには驚きを隠せません。地域の方の中には、漆の塗り直しを繰り返し、何十年と使っている方もいらっしゃいます。林業が盛んな井川地区の林業関係者たちのお昼を支えた井川メンパ 。現在では、デパートや通販、井川地区の隣にある川根本町にある「大井川メンパ 」で購入することができます。「井川メンパ 大井屋 」という店では修理もしてくれます。
静岡県静岡市の最北の地区・井川。南アルプスへの入り口でもあるこの地域で、弁当箱「井川メンパ 」は作られてきました。ヒノキの曲物に漆をしっかり塗り込んでおり、その丈夫さには驚きを隠せません。地域の方の中には、漆の塗り直しを繰り返し、何十年と使っている方もいらっしゃいます。林業が盛んな井川地区の林業関係者たちのお昼を支えた井川メンパ 。現在では、デパートや通販、井川地区の隣にある川根本町にある「大井川メンパ 」で購入することができます。「井川メンパ 大井屋 」という店では修理もしてくれます。福岡県 博多曲物(はかたまげもの)
 博多曲物は、福岡県粕屋郡志免町で作られています。創業400目年「博多曲物 玉樹」では、 18代目の女性が守り伝えています。博多曲物の起源は諸説ありますが、江戸時代より盛んに作られ、福岡市にある筥崎宮の神具として、古くから奉納されてきた伝統があります。アイテムによっては、表面に松やツル、梅の絵付けが施されています。絵付けされた曲物はとても珍しいですね。博多曲物には飯びつ、茶びつ、弁当箱などの生活用品や、茶道で使う建水、菓子器などがあります。
博多曲物は、福岡県粕屋郡志免町で作られています。創業400目年「博多曲物 玉樹」では、 18代目の女性が守り伝えています。博多曲物の起源は諸説ありますが、江戸時代より盛んに作られ、福岡市にある筥崎宮の神具として、古くから奉納されてきた伝統があります。アイテムによっては、表面に松やツル、梅の絵付けが施されています。絵付けされた曲物はとても珍しいですね。博多曲物には飯びつ、茶びつ、弁当箱などの生活用品や、茶道で使う建水、菓子器などがあります。長野県 木曽曲物
 駒ケ岳にほど近い、長野県塩尻市奈良井で作られているのは木曽曲物。他の産地と異なる特徴があります。それは、2種類の木を組み合わせて作ること。ほかの産地では1種類の木で作ることが多いのですが、木曽曲物では、曲がっている側板は木曽ヒノキ、その側板にはめられるフタ板と底板は木曽サワラを使っています。木曽サワラは吸水性・保湿力が高く、昔からおひつや寿司桶の材料として使われてきた木材です。
駒ケ岳にほど近い、長野県塩尻市奈良井で作られているのは木曽曲物。他の産地と異なる特徴があります。それは、2種類の木を組み合わせて作ること。ほかの産地では1種類の木で作ることが多いのですが、木曽曲物では、曲がっている側板は木曽ヒノキ、その側板にはめられるフタ板と底板は木曽サワラを使っています。木曽サワラは吸水性・保湿力が高く、昔からおひつや寿司桶の材料として使われてきた木材です。 昔から尾張藩の御用林調達地として大事にされてきた木曽地方は、寒冷地のため、木の成長がとても遅く、木目の詰まった良材の木材が採れます。そのため、曲物に使用できる材料の選択肢の幅が広く、木の性質に合わせて適材適所に使うことができ、2種類の木材を使うようになったそうです。「花野屋」では、多種多様な木曽曲物がそろっています。江戸時代の町並みを残す宿場町、奈良井の町並みにぴったりのアイテムをぜひ、見つけに行ってみてください。
昔から尾張藩の御用林調達地として大事にされてきた木曽地方は、寒冷地のため、木の成長がとても遅く、木目の詰まった良材の木材が採れます。そのため、曲物に使用できる材料の選択肢の幅が広く、木の性質に合わせて適材適所に使うことができ、2種類の木材を使うようになったそうです。「花野屋」では、多種多様な木曽曲物がそろっています。江戸時代の町並みを残す宿場町、奈良井の町並みにぴったりのアイテムをぜひ、見つけに行ってみてください。この他にも、三重県尾鷲市で作られている「尾鷲わっぱ」や群馬県中之条町入山地区の「入山メンパ 」などがあります。全国各地で曲物は作られ、その土地の歴史文化に合わせて変化していったようです。