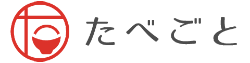目次
 「シードル」というお酒を知っていますか?りんご味のサイダーのようなシードルは、すっきりとした味わいで飲みやすく、女性にも人気が高いお酒です。りんごの産地として有名な青森県でもシードル工房や醸造所が新たにできたりと、シードルの勢いは今後ますます加速していきそうです。今回は青森県引前市にあるシードル工房「Kimori(キモリ)」へ取材し、シードルの製造方法やおすすめのシードルの楽しみ方、またそのほかに青森県から誕生したおすすめのシードルをご紹介します。
「シードル」というお酒を知っていますか?りんご味のサイダーのようなシードルは、すっきりとした味わいで飲みやすく、女性にも人気が高いお酒です。りんごの産地として有名な青森県でもシードル工房や醸造所が新たにできたりと、シードルの勢いは今後ますます加速していきそうです。今回は青森県引前市にあるシードル工房「Kimori(キモリ)」へ取材し、シードルの製造方法やおすすめのシードルの楽しみ方、またそのほかに青森県から誕生したおすすめのシードルをご紹介します。シードルとはどんなお酒?

ヨーロッパではワインと同じくらいポピュラーなアルコール飲料
 シードルとは、りんごや梨などの果実を発酵させてつくられるアルコール飲料のことを指し、イギリスでは「サイダー」と呼ばれます。フランスやスペイン、イギリスなどのヨーロッパ各国ではワインと同じくらいポピュラーなアルコール飲料として浸透しています。
シードルとは、りんごや梨などの果実を発酵させてつくられるアルコール飲料のことを指し、イギリスでは「サイダー」と呼ばれます。フランスやスペイン、イギリスなどのヨーロッパ各国ではワインと同じくらいポピュラーなアルコール飲料として浸透しています。日本では、大手メーカーの「ニッカウヰスキー」と「アサヒビール」がアップルワインとシードルをそれぞれ販売しているほか、りんごの生産地ではシードル工房やブルワリーでご当地の特色あるシードルが生産されています。
シードルのアルコール度数
シードルのアルコール度数は、造っている工房や種類によってさまざまですが、アルコール度数3%~6%が多いようです。シードルは発酵させる時間が長ければ長いほど、アルコールの度数が強くなります。同じ品種のりんごを同じように使ったとしても、発酵させる時期や時間、その時の温度や湿度などでも発酵度合いが変わるのだそうです。シードルの味を生み出す発酵時間
シードルには「スイート」や「ドライ」など、味のバリエーションがあります。この違いは、発酵期間の長さやシードルに使うりんごの品種によるのだそうです。発酵が長いと辛口になり、発酵期間が短いと、発酵されないまま残る糖分で甘口になります。同じりんごを使っても発酵時間によって辛口にも甘口にもなるのは、面白いですよね。青森県弘前市の「弘前シードル工房kimori」
 今回取材させていただいたのは、弘前シードル工房「kimori」代表の高橋哲史さんです。
今回取材させていただいたのは、弘前シードル工房「kimori」代表の高橋哲史さんです。弘前シードル工房「kimori」は、弘前市りんご公園の敷地内にある、三角屋根の建物。りんご畑に囲まれたこの建物の中に、シードルを醸造するためのタンクと、シードルを味わえる開放的なスペースがあり、訪れる人たちはりんご畑を眺め、シードルを味わいながらゆったりとした時間を過ごすことができます。
りんご農家がシードル作りを始めたきっかけ
 弘前のりんご農家だった高橋さんが、なぜシードルを作ることになったのか、その経緯をお伺いしました。
弘前のりんご農家だった高橋さんが、なぜシードルを作ることになったのか、その経緯をお伺いしました。高橋さん「平成20年に、青森県の津軽地方一円に雹(ひょう)が降り、雹によってりんごに傷がついてしまいました。りんごの実に傷が付くと、農産物として出荷することができませんし、傷から腐ってしまうので、やむを得ず多くのりんごを埋設処分したんです。手塩に掛けて育てたりんごを、捨てるしかないというのは非常に心苦しかったです。またりんごの産地はりんごの出来次第で地域経済に大きな影響を及ぼします。そんなりんごの出来に左右されないビジネスモデル(りんごを加工して無駄なく商品にする手段)によって、それが解決できるのでは?と考えました。」
りんご大国である青森県弘前市では後継者不足も深刻で、今後10年、20年で担い手のいない手付かずのりんご畑がどんどん増えてしまうという問題もあるのだそうです。後継者がいなければ、これまで脈々と受け継がれ、成長してきたりんごの木が絶やされてしまいます。りんごの生産が減ると地域の経済に影響が及びます。高橋さん「りんご農家の課題に見えて、経済がりんごに左右されるというのは実は地域の課題でもあるんです。このような課題を知ってもらうためには、まずりんご畑に来てもらって、りんごがどうやって育てられているのかを知ってもらう必要があると考えました。人が集まったときに、お酒があれば楽しい。
今のりんご畑があるのは、先代から受け継がれる技術や知識があるからだということを知ってほしい。りんご畑で、楽しい時間を過ごしてほしい。
そんな思いから、りんごのお酒を造ろう!となり、シードル造りが始まりました。」
 古くからのりんご農家の風習で、収穫が終わったりんごの木にひとつだけ実を残すことがあるのだそうです。今年の実りへの感謝をささげるとともに、来年の豊作を願い、畑の神様にささげるために残す、りんごの実。これを「木守り(きもり)」と言うのだそうで、「kimori」の由来はこの風習から来ています。
古くからのりんご農家の風習で、収穫が終わったりんごの木にひとつだけ実を残すことがあるのだそうです。今年の実りへの感謝をささげるとともに、来年の豊作を願い、畑の神様にささげるために残す、りんごの実。これを「木守り(きもり)」と言うのだそうで、「kimori」の由来はこの風習から来ています。先人たちが守り、築き上げてきたものを将来へと繋ぎたい、という思いが込められているのだそうです。
 高橋さんがシードル工房を構想し始めたのは平成20年。そこから徐々にりんご農家の仲間や賛同者を集め、6年の歳月をかけて、弘前シードル工房「kimori」は平成26年にオープンしました。原材料となるりんごの生産からシードルの製造まで、現在は4種類のシードルを通年で販売しているほか、りんごを使った新商品の開発、りんご農家の担い手育成などにも積極的に取り組んでいます。
高橋さんがシードル工房を構想し始めたのは平成20年。そこから徐々にりんご農家の仲間や賛同者を集め、6年の歳月をかけて、弘前シードル工房「kimori」は平成26年にオープンしました。原材料となるりんごの生産からシードルの製造まで、現在は4種類のシードルを通年で販売しているほか、りんごを使った新商品の開発、りんご農家の担い手育成などにも積極的に取り組んでいます。りんご畑で開催するイベントも盛況
毎年5月上旬、りんごの花が咲く時期に、弘前市りんご公園内では「シードルナイト」というイベントが開催されています。シードルをはじめとする青森県産のりんごのお酒を飲み比べしたり、音楽を楽しんだり、りんご畑の中でりんごを味わい楽しむイベントです。木陰で昼寝したり、りんご箱に座っておしゃべりしたり。りんご畑でゆるやかに過ごせる時間が、地域の人たちにも好評です。