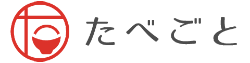目次
 甘辛くない角が取れた丸い味わい。微生物が生きているかのような自然あふれるもろみの香り。
甘辛くない角が取れた丸い味わい。微生物が生きているかのような自然あふれるもろみの香り。そんな「ホンモノの醤油」に、あなたは出会ったことがありますか?
日本では1%未満といわれる「木桶製法」で代々醤油を作り続けている、香川県小豆島のヤマロク醤油株式会社。
五代目の山本さんは、400年近く紡いできた伝統的な醤油作りや蔵を子供や孫、その先の世代に残していくことを使命に、日々に醤油作りと向き合っています。
今回は、そんな山本さんこだわりの醤油作りを見学するため、小豆島のヤマロク醤油の醤油蔵まで実際に足を運び取材を行いました!
ヤマロク醤油の歴史や想い

ヤマロク醤油の歴史
ヤマロク醤油の創業は、江戸時代の終わり~明治の始め頃。小豆島で醤油作りが始まったおよそ400年前までさかのぼります。ヤマロク醤油が、本格的に醤油作りを初めたのは終戦から4年後の昭和24年。三代目が醤油を搾る圧搾機を導入したことから醤油作りがスタートしたそう。
その後も伝統的な「木桶仕込み」で醤油を作り続け、今では都内の販売店で品薄状態になるほどの大人気!ヤマロク醤油がなぜ多くの人に支持されるのか、その理由を探ってゆきましょう。
5代目蔵人 山本さんの歩み
社会人になり思わぬ壁にぶちあたる
大学卒業後は小豆島に戻りたいと思っていた山本さん。小豆島で働くために地元の佃煮メーカーに就職したのですが、営業職だったため島ではなく大阪配属を言い渡されてしまったそう。島に後ろ髪を引かれながらも、張り切って社会人の第一歩を踏み出しますが、そこで思わぬ壁にぶつかります。
理想と現実のギャップ
素材にこだわったいいものを作っても安く買い叩かれる現実。添加物で日持ちを良くし、化学調味料で単価を下げたものが売れる仕組み。便利さや安さと引き換えに失われてゆく食の豊かさ。「ホンモノの食の追求」ではなく、「コストバリューの追求」が、食に熱い想いを持っていた山本さんの心をどんどん苦しめていきました。
実家の蔵を継ぐことを決意!
手間ひまかけて作ったものが、正しい価格で評価され売れる仕組み。顔の見えるものづくりから生まれる食の追求と、安心・安全。消費者も笑顔になれる方法を何かを考えた末、実家の蔵を継ぐことを決意します。この時、大学を卒業してから10年の歳月が経っていました。
おいしい醤油は木桶から生まれる
 日本に3000~4000本しかないといわれる木桶のうち、およそ1000本が小豆島で醤油作りのため使われています。
日本に3000~4000本しかないといわれる木桶のうち、およそ1000本が小豆島で醤油作りのため使われています。木桶に付着した白っぽいものはすべて、醤油の発酵を助けてくれる乳酸菌や酵母菌。およそ100種類近くの菌が一つの木桶に住み付いているのだそうです。
木桶にも一つひとつに個性がある
人にも個性があるように木桶にも個性があり、一つとして同じものはありません。太陽の当たり具合や、菌が多く生息する土壁からの距離、その年の天気によっても木桶に住み着く微生物が異なり、樽ごとに醤油の味や香りが変わるのです。シンプルですがとてつもなく奥の深い天然醸造。まさに木桶の数だけ醤油がある、10樽10色の世界と言えますね。
微生物が生きづく「蔵」
 蔵一面を見渡すと、壁や柱も木桶と同じくらいボロボロの状態。「建て替えないのですか?」と質問すると、「このボロボロの状態を保つことがおいしい醤油作りに欠かせないんですよ。」と山本さんは答えます。
蔵一面を見渡すと、壁や柱も木桶と同じくらいボロボロの状態。「建て替えないのですか?」と質問すると、「このボロボロの状態を保つことがおいしい醤油作りに欠かせないんですよ。」と山本さんは答えます。それもそのはず、壁や柱の土間には木桶以上に何百という乳酸菌や酵母菌が暮らしており、醤油の発酵を助けてくれるのです。
蔵を守ることは困難な道
だからこそ、木桶だけを残して蔵を新築すればよいといった単純な話ではなく、少しずつ手間暇をかけながら蔵を大きくしてゆく必要があります。微生物たちの家である「蔵」を守り続けていくことは、決して簡単な道のりではなかったのですね。
蔵を残すための「木桶職人復活プロジェクト」
日本で仕込み用の杉樽を造れるのは、大阪の堺市にある「藤井製桶所」1社のみ。「このままでは木桶を造れる職人がいなくなってしまう!」と危機感を覚えた山本さんは「木桶職人復活プロジェクト」と第して、友人3人と藤井製桶所まで前代未聞の修行旅に向かいます!このとき作り上げた杉樽は、ヤマロク醤油の名札とともに増築した蔵に置かれてました。4代目から受け継いだ「地獄のもろみまぜ」
 ホンモノの醤油を育てるには、とてつもない労力が掛かります。先代が「地獄のもろみまぜ」と呼ぶ、春から夏にかけて急激に発酵するもろみを混ぜる仕事もその一つ。
ホンモノの醤油を育てるには、とてつもない労力が掛かります。先代が「地獄のもろみまぜ」と呼ぶ、春から夏にかけて急激に発酵するもろみを混ぜる仕事もその一つ。夏は、もろみの発酵熱で樽の上が40度を超える、天然サウナ状態に。冬は、裏山(寒霞渓)から吹き下ろす通称「かんかけおろし」が芯から身体を冷やします。
熱くとも寒くとも決して休まない
すべてが手作業の重労働にも関わらず、1日でも休めば次の日の作業量が3倍になってしまうそう。一般的には1時間で混ぜ終わるものが3時間になってしまうため、休むことすら難しい過酷な状況。しかし、発酵を満遍なく進めるためにもろみ混ぜは必要不可欠。どれほど熱く寒くとも、おいしい醤油を造るため1日も休まず蔵へ向かいます。
材料と手間を惜しまない「再仕込み醤油」
 一般的な醤油は4~6カ月でできあがることがほとんどですが、ヤマロク醤油の「鶴醤(つるびしお)」は天然醸造の再仕込み製法。
一般的な醤油は4~6カ月でできあがることがほとんどですが、ヤマロク醤油の「鶴醤(つるびしお)」は天然醸造の再仕込み製法。再仕込み醤油とは一言でいえば「贅沢な醤油」。通常の醤油は、醤油麹に塩水を加えたもろみを熟成させて作りますが、再仕込みの醤油は塩水の代わりに醤油を使うので、材料と手間暇がかかるのです。
ヤマロク醤油でも大豆と小麦から作った麹の中に、2回の年を越した生醤油を加えて、発酵と熟成を行います。さらに3回、4回、5回と発酵と熟成を繰り返したもろみを2週間掛けて搾ることで、初めてホンモノの醤油が完成するのです。
蔵の見学は誰でも参加可能♪
 ヤマロク醤油では、普段見ることのできない「天然もろみ蔵」の見学体験を受け入れています。
ヤマロク醤油では、普段見ることのできない「天然もろみ蔵」の見学体験を受け入れています。予約の必要はなく、見学時間の指定もないで深く濃い醤油の世界をの思う存分堪能できますよ!