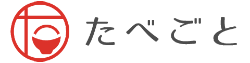目次
 手のひらにすっぽり収まるサイズ感で、デザインの豊富さと安定した形で人気のある蕎麦猪口(そばちょこ)。蕎麦猪口といったら蕎麦(そば)ですが、そばだけに使っていたらもったいない!
手のひらにすっぽり収まるサイズ感で、デザインの豊富さと安定した形で人気のある蕎麦猪口(そばちょこ)。蕎麦猪口といったら蕎麦(そば)ですが、そばだけに使っていたらもったいない!さまざまな場面で大活躍する蕎麦猪口の活用法とともに、おしゃれな蕎麦猪口をご紹介します。
そして、風情や趣がある骨董としての蕎麦猪口の見どころも紹介したいと思います。蕎麦猪口の奥深さを知って、生活に取り入れてみてくださいね!
そばのための食器じゃなかった!? 蕎麦猪口の意外な歴史

もとは懐石料理で使われていた高級食器
そばを食べるために欠かせない蕎麦猪口ですが、実はそばを食べるためのものとして誕生した食器ではなかったのです! 蕎麦猪口が作られるようになったのは、江戸時代のこと。製造がはじまったその当時、「蕎麦猪口」は「ちょこ」という名前で使われていました。17世紀前半、「ちょこ」と呼ばれていた蕎麦猪口は、上流階級の武家や将軍などが、和え物や塩辛などを盛って小鉢、懐石料理の向付(むこうづけ)として使われていたそう。また、上流階級の人が使っていたこともあり、当時の蕎麦猪口は、オーダーメイド品や華美な装飾などが施された高級な食器でした。
江戸中期の盛りそばブームが「蕎麦猪口」のきっかけ
この「ちょこ」が、そばを食べる時に使われるようになったのは、江戸時代中期のこと。江戸の町で盛りそばブームが起こり、蕎麦屋では、そばを盛ったせいろと一緒に出されるようになりました。大阪の名物蕎麦屋が伊万里(現在の佐賀県)に「ちょこ」を大量発注したことがきっかけで、「蕎麦を食べる時はちょこ」と、定着しはじめたという説もあります。
おしゃれにアレンジ! コーヒーやデザートまで。蕎麦猪口の使い方
 蕎麦猪口の持つかわいらしさは、昔から多く人を魅了してきました。そもそも蕎麦用の食器ではなかった蕎麦猪口の魅力は、見立ての楽しみがたくさん詰まっています。ちょっと一息つきたい時に湯のみやコーヒーカップとして使ってみたり、デザートを入れてみたり、花を生けてみたり。使い方は自由です。
蕎麦猪口の持つかわいらしさは、昔から多く人を魅了してきました。そもそも蕎麦用の食器ではなかった蕎麦猪口の魅力は、見立ての楽しみがたくさん詰まっています。ちょっと一息つきたい時に湯のみやコーヒーカップとして使ってみたり、デザートを入れてみたり、花を生けてみたり。使い方は自由です。現在では、おしゃれなものからスタイリッシュでシンプルなものなど、デザインも豊富。お手元の蕎麦猪口を見ながら、「何に使ってみようかな?」と自由な発想で考えるのも楽しいですよ! ここでは、皆さんが考える際のヒントとなるような、蕎麦猪口の使い方をご紹介します。
小鉢として
 江戸時代のように、和え物や煮豆、お漬物などを少し盛り付けると、上品な印象の食卓に。ほかにも、サラダやマリネなどを入れても素敵ですね! マリネや筑前煮のような具だくさんの料理を盛ると、色味も豊かで、食卓が華やかになります。
江戸時代のように、和え物や煮豆、お漬物などを少し盛り付けると、上品な印象の食卓に。ほかにも、サラダやマリネなどを入れても素敵ですね! マリネや筑前煮のような具だくさんの料理を盛ると、色味も豊かで、食卓が華やかになります。スープを入れて
 寒い季節には、スープを入れて食卓に並べましょう。どっしりとしている蕎麦猪口は、片手でも持ちやすく安定感抜群。お味噌汁、コーンスープなど入れるメニューも選びません。たまにはお椀を蕎麦猪口に変えてみると、気分が変わっていいですね!
寒い季節には、スープを入れて食卓に並べましょう。どっしりとしている蕎麦猪口は、片手でも持ちやすく安定感抜群。お味噌汁、コーンスープなど入れるメニューも選びません。たまにはお椀を蕎麦猪口に変えてみると、気分が変わっていいですね!デザートを入れて
 ぜんざいやあんみつの和スイーツはもちろん、ゼリーやプリンの洋スイーツを入れるのにもぴったり!自分でアイスクリームやカラフルなチョコレートをトッピングして、お手製パフェを子どもたちと作ってみても。
ぜんざいやあんみつの和スイーツはもちろん、ゼリーやプリンの洋スイーツを入れるのにもぴったり!自分でアイスクリームやカラフルなチョコレートをトッピングして、お手製パフェを子どもたちと作ってみても。コーヒーやお茶、日本酒も蕎麦猪口で
 コーヒーや緑茶をいただくにもぴったりです。蕎麦猪口の飾らない雰囲気が、ティータイムを和やかにしてくれます。大きめの蕎麦猪口はカップとして、少し小さめの蕎麦猪口は砂糖入れに使ってみてはいかがでしょうか。また、夜はしっぽり日本酒を飲むのにもおすすめです。
コーヒーや緑茶をいただくにもぴったりです。蕎麦猪口の飾らない雰囲気が、ティータイムを和やかにしてくれます。大きめの蕎麦猪口はカップとして、少し小さめの蕎麦猪口は砂糖入れに使ってみてはいかがでしょうか。また、夜はしっぽり日本酒を飲むのにもおすすめです。花器として

波佐見焼や有田焼からモダンデザインまで。蕎麦猪口15選
 日本各地を見渡すと、素材・デザインとさまざまな蕎麦猪口があります。呉須(藍色の顔料)で描かれた古風なデザイン、子どもが喜びそうな動物柄の北欧デザイン、シンプルなボーダーラインが可愛らしいデザインと個性豊か! 今回は、注目の蕎麦猪口をキーワード別にご紹介します!
日本各地を見渡すと、素材・デザインとさまざまな蕎麦猪口があります。呉須(藍色の顔料)で描かれた古風なデザイン、子どもが喜びそうな動物柄の北欧デザイン、シンプルなボーダーラインが可愛らしいデザインと個性豊か! 今回は、注目の蕎麦猪口をキーワード別にご紹介します!波佐見焼
1.伝統的な印判技法で作る蕎麦猪口 「東屋」
波佐見焼の蕎麦猪口。印判という旧来の方法で作られているため印刷のにじみ、欠け、ズレなどがありますが、それは職人さんの手作りだという証。森の上を鳥が楽しそうに飛んでいるかのような、シンプルながらもとても可愛らしいデザインは、食卓がほっこりとした優しい雰囲気に包まれそうです!2.太めのボーダーがかわいい! 和山の蕎麦猪口
太めのボーダーラインがとても可愛らしいカジュアルなデザインとなっています。ポップな赤、青、緑とポップな色合いです。全色揃えて、その日の気分で使う蕎麦猪口の色を決めるというのもいいですね!波佐見焼についてはこちらでもご紹介しています!