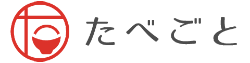目次
 1歳のお祝いに行う日本の伝統行事である「一升餅」をご存知でしょうか?赤ちゃんに一升分のもち米で作ったお餅を背負わせたり、踏ませたりして、赤ちゃんの健やかな成長をお祝いします。そのお餅を背負う赤ちゃんの可愛らしさといったら、思わず顔がほころんでしまいます!一升餅のお祝いは、地域によってやり方や準備するものが多少違います。ここでは一般的によく行われている方法や準備するものを中心にご紹介します!
1歳のお祝いに行う日本の伝統行事である「一升餅」をご存知でしょうか?赤ちゃんに一升分のもち米で作ったお餅を背負わせたり、踏ませたりして、赤ちゃんの健やかな成長をお祝いします。そのお餅を背負う赤ちゃんの可愛らしさといったら、思わず顔がほころんでしまいます!一升餅のお祝いは、地域によってやり方や準備するものが多少違います。ここでは一般的によく行われている方法や準備するものを中心にご紹介します!1歳になったら行う一升餅の意味とは?

一升餅のお祝いのやり方とは!
そもそも「一升餅」とは?
「一升餅」とは、一升分のお米(約1.8kg)を使って作るお餅を背負わせり、踏ませたりして、「一生食べ物に困らないように」、「これからの一生が健やかになるように」との願いを込めて、一歳までの成長を祝うとともにこれからの健やかな成長を祈る伝統行事です。お餅を背負って立ち上がれたら「身を立てられる」、座り込んでしまったら「家にいてくれる・家を継いでくれる」、転んだら「厄落としができた」といわれます。
・お餅を使ったお祝いの仕方
お祝いの仕方は、背負わせることが一般的ですが、ほかにも大きく3つあります。詳しく見てみましょう。| 背負わせる | リュックや風呂敷にお餅を入れて背負わせる一般的な方法です。 |
| 踏ませる | 一升餅を赤ちゃんに踏ませます。 |
| 抱かせる | 一升餅を赤ちゃんに抱かせます。座って抱かせても大丈夫です。 |
| 尻餅をつく | 尻餅をつかせることで、縁起がいいと言われます。 |
・準備するもの
| 一升餅 | 一升のもち米で作られたお餅です。大きいひと塊りの餅、小分けされているもの、ハート型のものと様々な一升餅があります。ほかにも、一升「餅」ではなく、一升パンや一升米もあります。 |
| リュックまたは風呂敷 | お餅を背負うためのものです。一升餅を買うとセットでついてくることが多いです。 |
・いつ行うの?
1歳の誕生日ではなくても、その周辺の休日や大安の日に行いましょう。親戚や祖父母と一緒にお祝いする場合は、事前に予定を合わせておきます。ただ、赤ちゃんの体調がすぐれない時は延期することをおすすめします。何キロのお餅が入っているの?
一升の重さとは約1.8kg。その一升分のもち米で作った一升餅は約2kgの重さになります。赤ちゃんによっては、この重さにびっくりして泣いてしまう子や嫌がる子もいるそうです。しかし、一升餅は赤ちゃんの健やかな成長を祈る行事なので、背負えなくても、立てなくても喜ばしいことと受け止められます。
さぁ、みんなで一生懸命頑張っている赤ちゃんを応援しましょう!
地域によって異なるお祝いの方法
 一升餅は、地域によっても呼び方や、やり方が違います。
一升餅は、地域によっても呼び方や、やり方が違います。例えば一升餅のほかに、「一生餅」、「誕生餅」、「踏み餅」、「立ったら餅」、「背負い餅・しょい餅」、「力餅」、「転ばせ餅」などと呼ばれています。
やり方も地域によってさまざまです。東日本では、一升餅を背負わせて座らせたり、歩けなくなるまでお餅の数を増やしたり、また、わざと転ばせたりする地域もあるそうです。わざと転ばせるのは、転ぶと「厄落としになる」・立てないと「家に長くいてくれる」ということを掛けているそうです。小さな餅をぶつけて転ばせる「ぶつけ餅」をする地域は、一見危なそうに見えますが、実際は受け止める用意をした上で、そっと突くようにしているそうですよ。
一方、一升餅を踏ませる「餅踏み・もちふみ」は、九州地方で多いそうです。「 早く丈夫に育つように」と餅を踏ませるそうです。少し変わったところでは、一升餅を抱かせるという地域もあるんですよ。
日本各地でこんなにも一升餅のお祝いの方法が違うなんてびっくりですね!みなさんの地域ではどのようにお祝いされていますか?この機会に、ご実家や義実家に地域のお祝い方法について、お話を聞いてみると新しい発見がありそうですね!
将来の才能を占う「選び取り」もしましょう!
 「選び取り」とは、赤ちゃんの前にさまざまな物を置いて、どれを手に取るかで将来の仕事や才能を占う伝統行事です。近年、一升餅のお祝いと一緒に行うことが増えてきました。
「選び取り」とは、赤ちゃんの前にさまざまな物を置いて、どれを手に取るかで将来の仕事や才能を占う伝統行事です。近年、一升餅のお祝いと一緒に行うことが増えてきました。「選び取り」で使われる定番アイテムと占い結果は、「そろばん=商才がある」「筆=学がつく、学者になる」「お金=お金に困らない」などです。
最近は現代的なアレンジも入っており、「箸=食べ物に困らない、料理人になる」「楽器=ミュージシャン・音楽家になる」「ボールなどスポーツ用品=そのスポーツで名を成す」などと、バリエーションが豊富。
また、アイテム実物を用意しなくても手軽に選び取りができる、選び取りカードも市販されていたり、一升餅を購入するとセットでついてくることもありますよ!