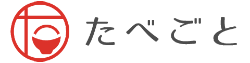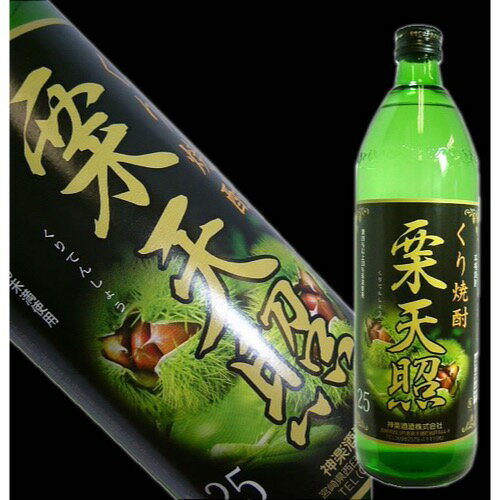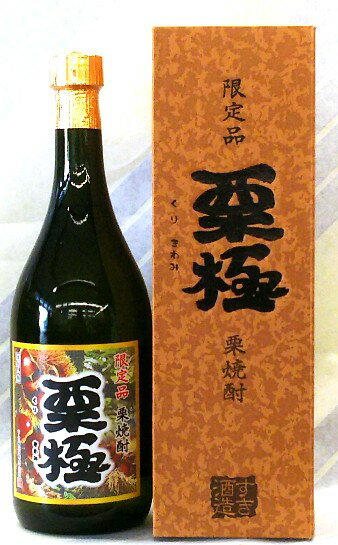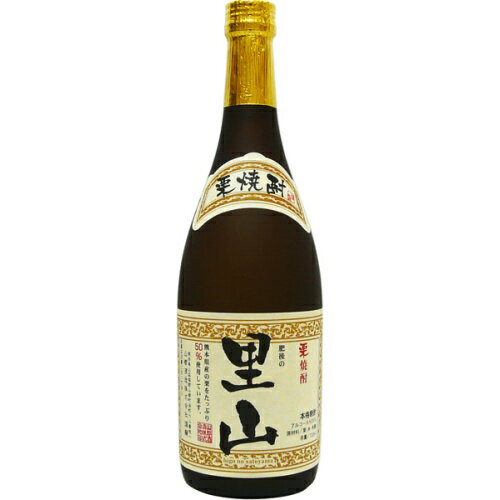栗焼酎生産の中心地〜愛媛・高知〜
2.おくりおくら
生産量第3位の愛媛県をはじめとする四国エリアは、江戸時代から栗栽培を行なっていたといわれる伝統ある地域です。栗焼酎生産の歴史も40年を超え、栗焼酎生産の中心となるエリアです。四国唯一の焼酎専業蔵の媛囃子(ひめばやし)による〈おくりおくら〉は地元のしろかわ栗と四国山地の伏流水を使用し、酒造が以前から作ってきた栗焼酎の原材料に米も加えることで新しい栗焼酎の味わいを生み出しました。3.奥伊予
また、同じく媛囃子の〈奥伊予〉は、酒造従来の製法で作られた栗焼酎を長期熟成して作られています。まろやかな舌触りの中に栗のうま味が活きた焼酎に仕上がりました。4.夢栗(むっくり)
一方、高知の〈夢栗〉は栗と栗の糖化に必要な米麹以外は使用せず、栗の使用率を85%にまで高めた贅沢な逸品。利き酒を重ね、通常は25度のものが多いアルコール度数を敢えて28度に設定するなど繊細な味への追求が光ります。5.四万十栗の栗焼酎
全国新酒鑑評会で金賞の最多受賞を誇る土佐鶴酒造の〈四万十栗の栗焼酎〉も、その名の通り四万十川流域の栗にこだわり造られています。原料に限りがあるため、季節によっては売り切れてしまう少量生産の限定販売です。古から受け継がれる丹波の栗〜京都・兵庫〜
6.古丹波
旧丹波国、現在の京都から兵庫県へと広がる丹波地方で平安時代から栽培されていたと記録の残る丹波栗は大粒で甘さが強いのが特徴。生産量こそ豊富ではありませんが、長い歴史と品質の良さで早くからブランド栗として知られています。自社農園の栗を一部使用し、清酒造りで培った米の発酵技術から栗の芳醇な香りとほのかな甘みを引き出した〈古丹波(こたんば)〉も、そんな貴重な丹波栗の良さを存分に活かした焼酎。低温ろ過にこだわり雑味の少ない繊細な味です。焼酎の本場が挑む栗焼酎〜宮崎〜
7.三代の松(みよのまつ)
本格焼酎の生産量日本一の宮崎県。南北に長く自然豊かな地理的環境から、米や麦、そばや栗などの原材料が生産され、多種多様な焼酎が作られてきた土地です。特に県北部の山地ではそばや雑穀の焼酎が有名。霧島を筆頭としたいくつもの山系からの豊かな湧き水と山の幸に支えられ、現在多くの栗焼酎が生産されています。 〈三代の松〉は延岡特産の生栗を地元の清流・祝子川の水で醸造した地産地消の栗焼酎。100年の歴史に裏付けられた焼酎造りの技術が素材の良さを引き出しています。
三代の松
・度数:25度
・原材料:栗・麦・米麹
・蒸留法:減圧低温蒸留
・蔵元メーカー:佐藤焼酎製造場(宮崎県)
・原材料:栗・麦・米麹
・蒸留法:減圧低温蒸留
・蔵元メーカー:佐藤焼酎製造場(宮崎県)
ロックとソーダ割りで楽しんでいます。美味しい〜!
焼酎は醒める時がきれいなので気に入ってます。
出典: Amazon
8.栗天照(くりてんしょう)
天照大神の神話が残る高千穂の〈栗天照〉は焼酎メーカー神楽酒造による栗焼酎です。雑穀焼酎に長年取り組んできた酒造がいくつもの改良を重ね、今の味に到達しました。クセの少ない主張しすぎないさりげなさが食中酒としても人気です。9.栗極(くりきわみ)
〈栗極〉は熊本と宮崎の県境にある人口2400人余りの須木村のすき酒造で作られています。地元小林の栗の鬼皮、渋皮を手作業で向き、甕仕込み、常圧蒸留と昔ながらの焼酎製法に実直に取り組んでいます。和甕でじっくりと熟成させた、手作り少量生産の限定商品です。豊富な栗生産量と焼酎醸造の技術の出会い〜熊本〜
10.肥後の里山
熊本県は全国の生産量の15%を占め、都道府県別収穫量が全国第二位の西日本最大の栗の産地です。特に県北部の山鹿市では昭和30年ごろに行政の指導のもと山間部に大規模栗農園が作られたという経緯があり、豊富な収穫量を誇ります。そんな熊本県産の栗だけを使用し焼酎を作るのは創業文政四年の酒蔵山都酒造。いくつもの賞を受賞した伝統ある酒蔵で、焼酎のバリエーションも豊富。長年培った焼酎造りの技術と西日本一の栗が出会い、すっきりとした味わいの栗焼酎〈肥後の里山〉が誕生しました。蒸留法や熟成期間で探す好みの味

低温?常圧?蒸留法の違い
本格焼酎と呼ばれる焼酎乙類は、自然の原料を用い昔ながらの単式蒸留で作られています。単式蒸留の中でも、蒸留方法は大きく2つに分けられ、それぞれできあがる焼酎の味に特徴がみられます。500年もの歴史を持つ昔ながらの「常圧蒸留」は、原料の特徴を引き出し力強い味わいになるのに対し、1970年代前半に登場した「減圧蒸留」は、蒸留機内部の気圧を下げることで沸点を下げ低温で蒸留できるため、口当たりの軽いソフトな印象になります。焼酎の個性を楽しみたい方は「常圧蒸留」の焼酎を、軽い飲みやすさを求める人は「減圧蒸留」の焼酎を…と、自分の好みを探して飲み比べてみるのもいいですね。熟成期間が生み出す新たな味
一般的に焼酎は1〜3カ月の貯蔵期間で出荷されますが、味の変化を期待し、あえて熟成させて販売するものも多くあります。製造から3カ月〜6カ月熟成する頃にはできたての焼酎の持つ刺激臭が減少、6カ月〜3年が経つ頃には香りが安定し、味も丸くなります。さらに、古酒と呼ばれる3年以上寝かせたものは味のまろやかさが増加し、独自の香りを漂わせるようになります。熟成期間も焼酎を選ぶポイントのひとつと言えそうです。おすすめの飲み方
 日本各地の栗焼酎を紹介してきましたが、おすすめの飲み方には共通点があります。栗焼酎はどれも香りや甘みがすっきりとしていて、クセがなく飲みやすいのですが、逆に強い味覚とミックスしてしまうとその特徴を存分に味わいにくいのです。そんな栗焼酎の味わいを感じられる飲み方を紹介します。
日本各地の栗焼酎を紹介してきましたが、おすすめの飲み方には共通点があります。栗焼酎はどれも香りや甘みがすっきりとしていて、クセがなく飲みやすいのですが、逆に強い味覚とミックスしてしまうとその特徴を存分に味わいにくいのです。そんな栗焼酎の味わいを感じられる飲み方を紹介します。