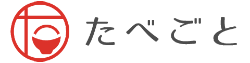目次
 雪どけと共に旬がやってくる春の味覚・山菜。最近は、八百屋以外にスーパーでもその姿を見かけるようになり、以前よりずっと身近な食材になったように感じます。ただ、中には下処理の方法や食べ方がわからず敬遠している人もいるのではないでしょうか。
雪どけと共に旬がやってくる春の味覚・山菜。最近は、八百屋以外にスーパーでもその姿を見かけるようになり、以前よりずっと身近な食材になったように感じます。ただ、中には下処理の方法や食べ方がわからず敬遠している人もいるのではないでしょうか。ぜんまいやわらびなどなじみのある種類から、「みず」や「あいこ」などのあまり見かけない種類まで、全15種類の山菜の特徴や旬の時期、下処理方法などまとめてご紹介します。
「山菜」は食用の自生植物の総称。春の山菜は3月頃から採取!

山菜とは?
「山菜」と聞くと、多くの人はわらびやぜんまいなどを思い出すのではないでしょうか。ところが、本来の意味は自然の中で自生している植物のうち、「食べることができる野草」を総称して示す言葉なのです。最近ではウドやフキのように栽培されている山菜もたくさんありますが、もとは収穫できるまでに長い年月がかかるため、大量生産には不向きな植物とされていました。ふきのとうをはじめ雪解けから芽吹くものが多く、春の訪れを告げる食の風物詩として日本の食文化にも深く根付いています。
山菜にも旬はある?
 それぞれ食べるのに最適な旬の時期はあります。よもぎやぜんまいなどは「春の山菜」、ヤマブドウやきのこ類、栗などは「秋の山菜」と呼べるでしょう。
それぞれ食べるのに最適な旬の時期はあります。よもぎやぜんまいなどは「春の山菜」、ヤマブドウやきのこ類、栗などは「秋の山菜」と呼べるでしょう。「春には苦みを盛れ」と言って、昔から春の山菜が持つ独特の苦味は、冬の寒さで縮こまった体を目覚めさせるための刺激として、若葉が出る頃に食べられてきました。ほかにも、1月7日には「七草がゆ」を食べる風習がありますが、これは体に良い食材を摂ることで無病息災を願ったことが元になっています。春の山菜が、昔から栄養価の高い植物として知られていたことがわかりますね!
旬の時期や特徴は?下処理方法や保存方法も!春の山菜15種類
1. よもぎ
和製ハーブとして身近な山菜の一つ。よもぎ餅など和菓子でもおなじみですね。河原や土手などに自生していることが多いので、子供の頃に摘んだことがある懐かしい野草ではないでしょうか。日本全国で見られる多年草ですが、若葉はえぐみ・苦味が少ないので、収穫に適した3〜5月の早いうちに摘むことをおすすめします。ギザギザの葉っぱが毒草の「トリカブト」に似ているので要注意です。| 名前 | よもぎ(キク科ヨモギ属) |
| 収穫時期 | 3月上旬~5月下旬頃 |
| 調理方法 | 草団子などの和菓子、パンなど |
| 下処理方法 | 塩と重層を入れたお湯で約2分。ゆでた後は冷水で約20分。 若葉や新芽の場合はゆでるだけでも食べられる。 |
| 保存方法 | 下ゆでした後、密封袋で冷凍庫へ。 |